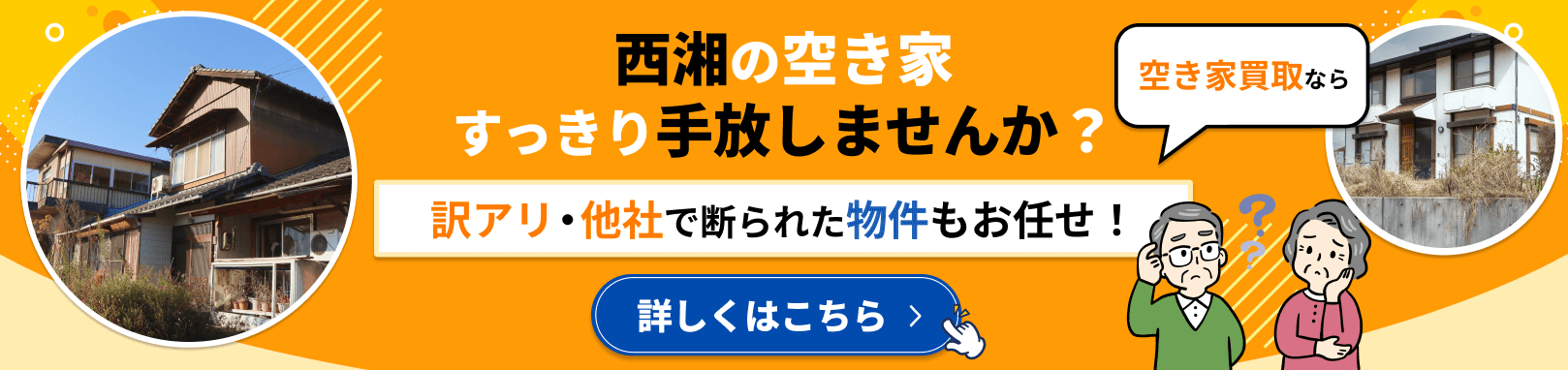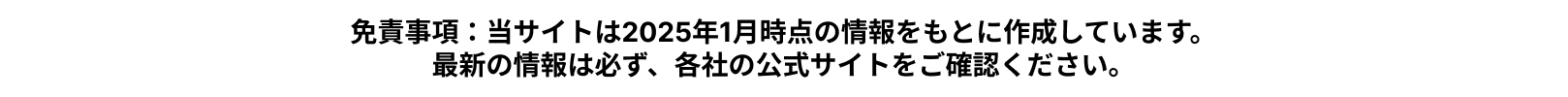不動産を共有名義で所有していると、そのままにしがちです。そして、共有名義のまま相続しようかと思っている方もいるでしょう。
しかし、共有名義で所有している不動産の相続は、リスクが高いと言えます。不動産を平等に分けられると思われがちですが、実はリスクがあるため、注意が必要です。
この記事では、相続不動産の共有名義のリスクや解消方法、手続きについて解説していきます。共有名義の不動産を相続しようか検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下の記事では、西湘エリアの空き家について触れているサイトなので、参考にしてみてください。
相続不動産の共有名義とは?

相続によって取得した不動産が複数人の名義で登記される状態を「共有名義」といいます。例えば、両親の不動産を兄弟で平等に相続した場合、それぞれが持分(持ち分割合)を所有することになります。
このように、ひとつの不動産に複数人の権利が存在する状態が共有名義です。
共有名義には、相続人全員が平等に権利を持つというメリットがある一方で、売却・賃貸・管理などを行う際には「共有者全員の同意」が必要になるという制約もあります。そのため、共有名義のまま放置すると、相続人同士の意見の不一致や手続きの複雑化など、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。
共有名義を正しく理解することは、相続後の不動産管理や売却をスムーズに進めるうえで非常に重要です。
共有名義の不動産を相続する場合の条件

共有名義の不動産を相続する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
それぞれの条件について解説していきます。
共有者全員の同意が必要
共有名義の不動産を相続する場合、共有者全員の同意が必要です。
不動産を売却したり、第三者に貸し出したりするといった手続きでは、共有しているすべての相続人の同意が求められます。仮に1人でも反対する共有者がいれば、取引は成立せず、手続きが進められません。
そのため、共有名義での相続は手間や時間がかかるだけでなく、将来的な活用や処分の自由度が著しく制限されます。共有名義の不動産を相続する際は、共有者間でしっかりと話し合い、合意を得る必要があります。
被相続人の持分のみを相続する
共有名義の不動産を相続するケースでは、被相続人が持っていた持分のみを相続する形となります。つまり、他の共有者の権利には影響を与えず、相続人は被相続人の保有していた割合だけを新たに取得します。
そのため、共有状態はそのまま引き継がれ、相続人が単独で不動産全体を自由に扱うことはできません。親が不動産を兄弟と共有していた場合であれば、親の持分のみを子が相続し、他の兄弟の権利には干渉できないということです。
この持分相続によって、共有者が増えることもあり、管理や処分が複雑になる傾向があります。
登記手続きには共有者ごとの申請が必要
共有名義の不動産相続では、登記手続きに各共有者がそれぞれの名義で申請しなければいけません。たとえば、親名義の不動産を兄弟で相続する際には、相続人全員が法定相続分や遺産分割協議に基づいて登記を確定し、持分に応じた名義で登記申請を行います。
このとき、単独での手続きは認められず、全員の同意と署名が必要です。また、必要書類として以下を揃える必要があります。
- 被相続人の戸籍
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
共有名義登記は法的効力を持つため、後のトラブル回避のためにも確実に対応しましょう。
相続税は持分に応じて課税される
共有名義となっている不動産の相続では、相続税が各相続人の持分割合に応じて課税されます。
たとえば、不動産を兄弟で2分の1ずつ相続した場合、それぞれの持分に対して課税される仕組みとなっています。課税評価額は固定資産税評価額などを基に算出され、各相続人が割合に応じた相続税を納める義務があります。
また、特例や控除の適用も個別に判断されるため、持分に見合った負担を計算しなければなりません。共有名義であることにより、他の相続人と手続きが重なる場面も多いため、納税時には事前の準備が必須です。
相続不動産の共有名義を解消せずに放置するリスク

相続する予定の不動産を享有名義のままにしておくと、以下のようなリスクが懸念されます。
それぞれのリスクについて解説していきます。
売却・処分が難しくなる
相続した不動産を共有名義のままにしておくと、売却や処分が難しくなるというリスクがあります。共有名義では、全ての共有者の同意がなければ意思決定ができません。
そのため、1人でも反対する人がいれば、取引は成立しません。相続人同士で意見が分かれている場合や、遠方に住んでいて連絡が取りづらい場合には、売却の機会を逃すこともあります。
また、不動産市場の状況が変化する中でタイミングを逃すと、資産価値が下がるリスクも懸念されます。共有名義であることが原因で、速やかな資産活用が妨げられることがあるため、将来的な方針を早い段階で共有者全員と話し合うことが大切です。
不動産の権利関係が複雑になる
共有名義のままの不動産相続では、権利関係が複雑化する恐れがあります。
たとえば、共有者の1人が亡くなれば、その持分が新たな相続人に引き継がれ、共有者が増加する可能性があります。結果として、全員の同意を得ることが難しくなり、意思決定が停滞するリスクが高まるでしょう。
また、共有者の所在が不明になったり、意思が対立したりするケースも見られ、法的手続きが必要となることも珍しくありません。このように、共有名義を維持することで不動産の管理が困難になり、将来的なトラブルの火種となるリスクがあるのです。
管理・修繕費の負担割合でトラブルになりやすい
相続した不動産が共有名義のままだと、管理や修繕に関する費用負担をめぐってトラブルが発生しやすくなります。
建物の老朽化で修繕が必要になった場合でも、共有者全員の合意がなければ工事が進められません。費用の分担でも、持分に応じて公平に負担するのが原則ですが、生活状況や経済力の違いから、意見が食い違うことも予想されます。
特に、不動産を利用していない共有者が費用負担に応じないケースでは、管理が行き届かず資産価値が低下する恐れもあるので注意が必要です。
持分割合に応じて税負担が発生する
共有名義の不動産を相続した場合、各相続人には持分割合に応じた税負担が発生します。
持分が3分の1であれば、その割合に見合った税額を納める必要があります。ただし、納税通知書は代表者1人に送付されるケースが多く、他の共有者と分担の合意が取れていないと、支払いや費用負担をめぐるトラブルに発展するリスクを抱えることになります。
また、未納があった場合には、全体に延滞金や差押えが及ぶ可能性も高まるでしょう。共有名義では責任の所在があいまいになりやすく、協議が難航する原因にもなります。
結局、相続不動産の共有名義はどうしたらいいの?

相続で共有名義になった不動産は、できるだけ早めに整理・解消することが望ましいです。共有のまま放置しておくと、将来の売却・管理・相続が複雑化し、意見の対立や手続きの停滞を招くリスクがあります。そのため、まずは共有者同士で話し合いを行い、今後の方針を明確にすることが大切です。
具体的な対応方法としては、次のような選択肢があります。
・他の共有者の持分を買い取って単独名義に変更する(1人が不動産を引き継ぐ場合に有効)
・共有者全員の合意で売却し、利益を分配する(現金化して平等に分けたい場合)
・共有者間で話し合いが難しい場合は、専門家に相談する(司法書士・弁護士・不動産会社など)
共有名義のままにするか、解消するかの判断はケースによって異なりますが、「誰がどのように使うのか」「維持費をどう負担するのか」を明確にしておくことがトラブルを防ぐ第一歩です。迷ったときは、早めに信頼できる専門家へ相談し、最適な解決策を見つけましょう。
相続不動産の共有名義を解消する方法

相続する予定の不動産の共有名義を解消するには、以下の方法が有効です。
それぞれの方法について解説していきます。
共有者間の持分売買で単独名義にする
相続した不動産の共有名義は、共有者間で持分を売買し、単独名義に変更することで解消できます。共有者が持分を他の相続人に売却することで、1人の所有者にまとめることが可能です。
共有者が複数いると、不動産の活用や売却が難しくなるため、単独名義にすることで意思決定がスムーズになります。
ただし、売買にあたっては時価での取引となり、譲渡所得税が発生する場合もあります。また、売買に合意が得られない場合は成立しないため、事前の話し合いが必要です。
遺言書で不動産の相続人を指定する
相続不動産の共有名義を解消する方法として、被相続人が遺言書で相続人を特定する手段があります。
遺言書があれば、不動産を特定の1人に相続させられるため、共有名義によるトラブルを防ぐことが可能です。たとえば「長男に自宅不動産を相続させる」と記載された公正証書遺言があれば、他の相続人との共有状態を避けられます。
共有名義を望まない場合には、遺産分割協議に頼らず、確実に意向を反映させる手段として有効です。ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないよう、財産全体のバランスを考慮した内容にする必要があります。
換価分割を活用する
換価分割とは、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。共有名義のままでは、使用や管理に支障をきたす場合があるため、現物ではなく金銭で公平に分けたいと考える方に適しています。
換価分割を行うには、相続人全員の合意が必要であり、売却の手続きも共同で進めることになります。売却後は、不動産の管理義務や税負担も消滅するため、トラブルの予防にもつながるでしょう。
代償分割を活用する
代償分割とは、相続人のうち1人が不動産を取得し、他の相続人にはその持分相当額を現金などで支払う方法です。これによって、相続した不動産の名義を一本化することが可能になります。
代償分割では、遺産分割協議の合意が前提となるため、他の相続人と調整することが不可欠です。この分割方法によって、不動産の管理や売却の自由度が高まるため、将来的なトラブルの予防にも効果的です。
特に、相続人が遠方に住んでいる場合や、不動産を活用する意向が明確な場合には、有効な選択肢となります。
第三者に自己持分を売却する
相続によって取得した不動産の共有名義は、自己の持分を第三者に売却することで解消できます。共有者間での協議が難航した場合や、単独での利用が見込めないときに有効です。
民法上、共有者は自己の持分を自由に譲渡できるため、合意がなくても外部に売却することは可能です。しかし、共有状態のまま売却されると、買主は他の共有者と不動産を管理することになり、購入希望者が限定されます。
そのため、市場価値よりも低い価格での売却になることが多く、損失を被る可能性もあります。
土地の場合は分筆がおすすめ!
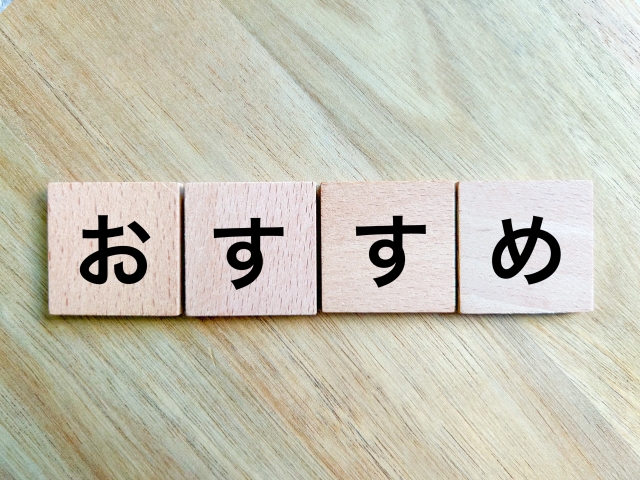
相続した土地を共有名義を解消する方法として、有効なのが分筆です。分筆とは、1筆の土地を複数に分けて、それぞれ単独名義に変更する手続きです。
共有者ごとに所有区画を分けることで、各自が自由に利用や売却を行えるようになります。分筆により、税金の支払いは個別の土地に対して課されるため、責任の所在が明確にすることが可能です。
土地の名義が複数人で名義している場合は、分泌を検討してみましょう。
分筆で相続する場合の注意点
土地を分筆して相続する場合には、いくつかの注意点があります。
まず、分筆には正確な測量が必要であり、専門家による立ち合いや登記申請が伴います。また、分筆後の各土地が建築基準法上の要件を満たさなければ、建物の建築や売却に制限が生じるでしょう。
さらに、共有者全員の同意がなければ手続きは進められないため、事前の話し合いが不可欠です。相続税の評価額にも影響が出ることがあるため、税理士への相談も検討しましょう。
不動産を相続する手順

不動産の相続は、以下の手順で進めるのが一般的です。
それぞれの手順について解説していきます。
相続人の確定と遺産分割協議
不動産相続の最初の手順となるのが、相続人の確定と遺産分割協議です。
まずは戸籍謄本を収集し、法定相続人を漏れなく確定させる必要があります。その上で、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定します。不動産が共有名義となるか単独で引き継ぐかも、この段階で決めましょう。
協議の結果は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、全員の署名・押印をもって成立します。ここでの合意が不動産登記や税務申告の土台となるため、全員が納得する内容となるようにしましょう。
合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停が必要になります。
相続登記を行う
遺産分割協議がまとまり、相続する不動産の内容が決定したら、相続登記に移ります。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するための登記手続きです。2024年4月からは相続登記が義務化され、原則として相続の開始を知った日から3年以内に行う必要があります。
手続きでは、以下の書類を揃え、法務局へ申請します。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人の戸籍
- 住民票
- 固定資産評価証明書
共有名義で登記する場合は、各相続人の持分割合も明記されます。登記が完了することで、相続人として正式に不動産の権利を有することになり、売却や活用の前提が整います。
登記簿謄本を取得する
相続登記が完了した後は、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。登記簿謄本は不動産の所有者や持分割合、権利関係を公的に証明する書類であり、売却や金融機関とのやり取りでも必要となる場面が多くあります。
取得は法務局の窓口やオンライン申請により可能で、相続登記の完了後、数日程度で反映されるのが一般的です。登記簿謄本に記載されている内容に誤りがないかを確認し、万一の記載ミスがあれば、速やかに訂正手続きを行ってください。
また、共有名義の場合は各相続人の持分が明記されているため、トラブル防止にも役立ちます。不動産の正確な権利情報を把握するために、取得は必ず行いましょう。
不動産会社に査定を依頼する
登記簿謄本の取得までが終わったら、一般的な不動産売却を進めます。まず不動産会社に査定を依頼し、以下の要素を踏まえて価格が算出されます。
- 相続による取得時点の状況
- 立地
- 建物の状態
- 周辺の取引事例
査定には机上査定と訪問査定があり、実際に売却を進めるなら、現地での確認を伴う訪問査定が望ましいです。査定価格を基に売却の可否を判断するため、複数の不動産会社に依頼し、内容を比較検討することも有効です。
共有名義の場合は、全員の同意が必要となるため、査定結果をもとに共有者間で意見をすり合わせることが求められます。
媒介契約を結んで販売活動を行う
不動産売却を依頼する会社を決めたら、媒介契約を結び、販売活動を開始します。媒介契約とは、不動産会社に売却を正式に依頼する契約で、契約形態には以下の3種類があります。
- 専属専任媒介
- 専任媒介
- 一般媒介
契約を結ぶことで、不動産会社は物件情報を公開し、販売活動を本格的に開始します。売主は、内覧や交渉に備える必要があります。
共有名義の不動産を売却する場合、共有者全員の同意を得た上で媒介契約を結ぶことが前提となるため、事前の協議と合意形成が必須です。
買い手と売買契約を締結する
購入希望者が現れて条件に合意すれば、売買契約を締結します。売買契約では以下の詳細な取り決めを行います。
- 売買価格
- 引き渡し時期
- 支払い方法
- 物件の状況
契約は原則として書面で交わされ、重要事項説明を受けた後で、売主と買主双方が署名・押印し、手付金が支払われます。共有名義の不動産売却では、共有者全員が契約に同席・署名する必要があり、1人でも同意していないと契約は無効となります。
また、売主側には契約後の瑕疵担保責任が生じる可能性があります。その後は決済・引き渡しが行われ、売却が完了となります。
共有名義の相続不動産は売却がおすすめ!メリットは?

相続で不動産を共有名義にしたまま放置すると、権利関係が複雑化し、後々トラブルに発展する可能性があります。特に相続人が複数いる場合、管理や売却の意思決定に時間がかかることも珍しくありません。
そのため、早い段階で不動産を売却し、資産を整理するのが効果的です。ここでは、共有名義の相続不動産を売却することで得られる主なメリットを紹介します。
共有名義をそのままにしておくリスクを避けるためにも、売却による3つのメリットを具体的に見ていきましょう。
トラブルを未然に防げる
共有名義のまま不動産を所有していると、管理方針や売却の是非をめぐって共有者同士の意見が対立することがあります。さらに、共有者の一人が亡くなると新たな相続人が増え、権利関係が複雑化して売却が難しくなるケースもあります。
売却を行えば、共有状態を解消でき、相続人同士の摩擦を防ぐことができます。加えて、売却によって現金化することで、今後の資産管理もシンプルになり、不要なトラブルを未然に防ぐことが可能です。
管理や維持の負担がなくなる
共有名義の不動産は、修繕費や固定資産税、清掃などの維持管理にかかる費用を共有者全員で分担する必要があります。しかし、誰がどの費用を負担するかでトラブルになることも少なくありません。
売却することで、こうした日常的な管理コストや手間から解放されます。特に、空き家状態の不動産では老朽化や倒壊のリスクもあるため、早期売却は経済的にも合理的な選択です。負担を減らし、資産を有効活用できる点が大きなメリットといえるでしょう。
資産を公平に分配できる
共有名義のままでは、誰がどれだけ使うか・どのように維持するかを巡って不公平感が生まれやすくなります。不動産を売却して現金化すれば、持分割合に応じて平等に分配できるため、相続人同士の不満を防ぐことができます。
また、現金化によって資金を自由に使えるようになり、相続税や生活費などの支払いにも充てられます。感情的な対立を避け、円満に相続を終えるためにも、売却による分配は有効な方法です。
共有名義の相続不動産を売却する方法

共有名義の相続不動産を売却する場合、権利関係が複雑なため、通常の不動産売却よりも慎重な手続きが求められます。特に、共有者が複数いる場合は、売却条件や方針をすり合わせることが不可欠です。
スムーズに売却を進めるには、正しい方法を理解し、状況に合った手段を選ぶことが大切です。
それぞれの方法にはメリットと注意点があります。以下で詳しく見ていきましょう。
共有者全員の合意で売却する
最も一般的でスムーズな方法は、共有者全員が同意して不動産を売却するケースです。全員の合意を得たうえで、不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結んで販売活動を行います。
共有者が複数いる場合、代表者を決めて手続きを進めると効率的です。全員の意見を尊重しながら進めることで、信頼関係を保ちつつ円満に売却できます。手続きの負担はやや多いものの、最もトラブルが少ない方法です。
自分の持分のみを売却する
他の共有者が売却に反対している場合、自分の持分だけを第三者に売却することも可能です。ただし、購入希望者が限られるため、売却価格は下がる傾向にあります。
最近では、共有持分を専門的に買取する業者も増えており、現金化を急ぎたい場合には有効な選択肢です。売却前に他の共有者へ意向を伝えておくことで、トラブルを回避できます。短期間で資産を整理したい方に向いています。
専門の不動産会社に相談して進める
共有名義不動産の売却は、登記・税金・相続人調整など専門的な知識が必要になるケースが多いため、専門の不動産会社や司法書士への相談が効果的です。
専門家を介すことで、法的手続きを正確に行い、共有者間の調整もスムーズに進められます。相続登記が未完了の場合や、共有者同士の関係が複雑な場合にも、第三者のサポートによって円満な解決が可能です。
相続不動産を売却する際の不動産会社の選び方

相続不動産をスムーズに売却するには、実績があり信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。相続案件は手続きや税務が複雑なため、経験の浅い会社に依頼するとトラブルにつながることもあるので注意が必要です。
適切な会社を選べば、法的な確認や共有者間の調整もサポートしてもらえるため、安心して売却を進められます。ここでは、不動産会社を選ぶ際の重要なポイントを紹介します。
これらのポイントを意識することで、納得できる価格と条件での売却が実現しやすくなります。以下で詳しく解説します。
相続や共有名義の売却実績が豊富な会社を選ぶ
相続や共有名義の不動産は、登記・税務・持分調整など通常よりも複雑な対応が必要です。そのため、相続案件を多く扱っている不動産会社を選ぶことが成功の鍵となります。
公式サイトで実績を確認し、相続専門スタッフや士業連携の有無もチェックしましょう。経験豊富な会社なら、法的手続きやトラブル回避のサポートも期待でき、安心して任せられます。
査定や説明が丁寧で信頼できる担当者を選ぶ
相続不動産の売却では、複雑な登記や税金の説明を分かりやすくしてくれる担当者が重要です。査定内容や販売方針を丁寧に説明し、質問に明確に答えてくれる担当者は信頼できます。
また、メリットだけでなくリスクや注意点も正直に伝えてくれる担当者は誠実です。初回面談や対応スピードもチェックし、安心して任せられる人を見極めましょう。
複数社を比較検討して選ぶ
不動産会社によって査定額や販売方法は異なります。1社だけで決めず、複数社に査定を依頼して比較することが大切です。高すぎる査定額を提示する会社は成約につながりにくいため、根拠のある価格設定かどうかを確認しましょう。
さらに、販売戦略やサポート体制も比較することで、自分の目的に合った会社を選べます。複数社を比較することで、納得度の高い取引が実現するでしょう。
西湘エリアの相続不動産ならハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめ

相続した不動産の売却や活用を検討している方には、ハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | ハウスドゥ 小田原市役所前 |
| 会社名 | 株式会社Forest field |
| 所在地 | 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪531-6 |
| 電話番号 | 0465-34-2555 |
| 公式HP | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/satei/ |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31148号 |
小田原市や南足柄市を中心に、近隣地域に精通したスタッフが在籍し、地域密着型のサービスを提供しています。相続不動産の売却はもちろん、再建築不可物件や築古物件など、他社では対応が難しいケースにも対応可能です。
特に、売却後も住み続けられる「ハウス・リースバック」制度は、資産活用の選択肢として注目されています。相続や税務に関する相談にも対応しており、専門的な知識を持つスタッフが丁寧にサポートします。
相続不動産に関する悩みや不安を抱えている方は、一度相談してみることをおすすめします。
また、ハウスドゥ 小田原市役所前の空き家買取や不動産売却について気になる方はお問い合わせしてみてください。
まとめ
共有名義で相続した不動産は、相続人全員の同意が前提となるため、管理や処分において多くの課題が想定されます。これらのトラブルを避けるためには、分筆や持分の売却といった解消策を早期に検討することが重要です。
相続手続きは、相続人の確定から登記、売却に至るまで多くの手順があり、それぞれに法的・実務的な注意点が伴います。そのため、不動産会社など専門業者の支援を受けることで、スムーズな対応ができます。
共有名義のまま放置せず、今後の活用や売却を見据えた対策を講じることで、安心して相続に対応することが可能です。