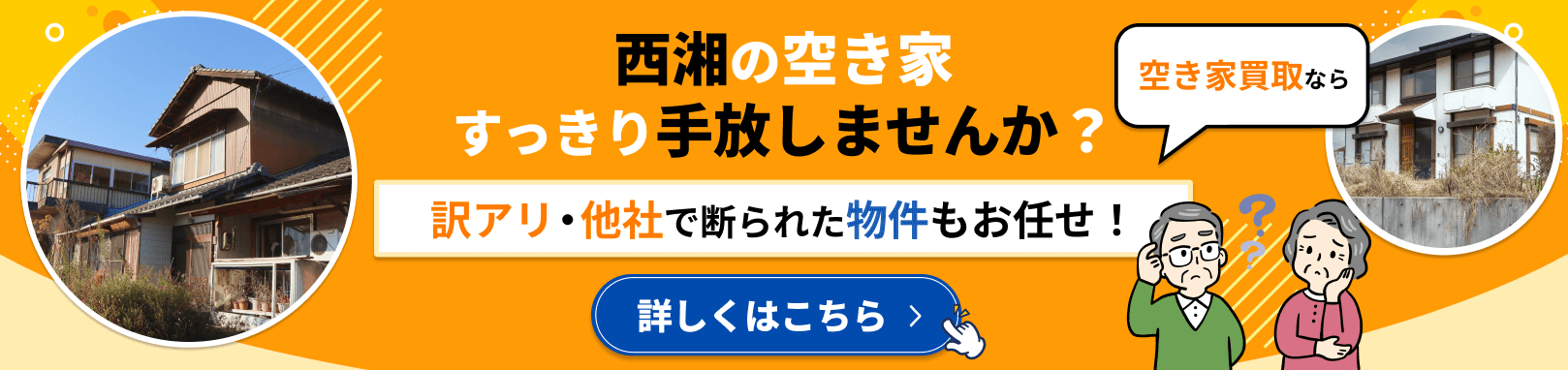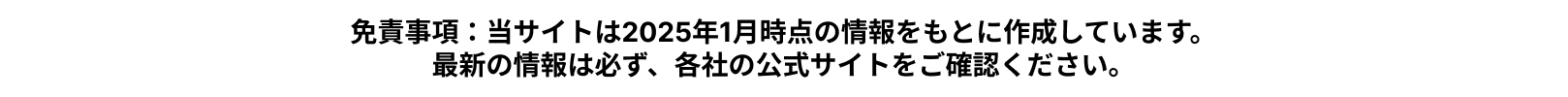「再建築不可物件は売却できる?」
「売却するにはどうすればいい?」
再建築不可物件を売却する場合、一般的な不動産売却とは異なり、時間がかかることになります。建て替えや増築ができない物件は、買い手にとって魅力的とは言えず、優先的に買ってもらえない可能性があります。
再建築不可物件を売却する方法としては、再建築不可物件のまま売却するのと、再建築可能な物件にして売却するの2パターンがあります。どちらの場合でも売却は可能ですが、スムーズにいくとは限りません。
この記事では、再建築不可物件の売却方法や相場、注意点について解説していきます。再建築不可物件の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下の記事では、西湘エリアの空き家について触れているサイトなので、参考にしてみてください。
再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、建築基準法に定められた接道義務を満たしていない土地上にある建物のことを指します。再建築不可物件に該当する場合、既存建物を解体しても新たな建物を建てられず、建物の修繕や増改築にも制限がかかります。
再建築不可物件は、資産価値が下がりやすく売却活動に苦戦するリスクもありますが、収益物件や資材置き場としての活用にも使えます。一般的には、売れにくい物件として認識されています。
再建築が不可とみなされる条件

再建築が不可とみなされる条件は、建築基準法第43条に基づき定められています。具体的な条件は、以下の通りです。
- 建築基準法上の道路と接していない
- 建築基準法上の道路と接している幅が2m未満
- 建物の敷地が幅員4m未満の道路に接している
- 接している道路が建築基準法に準じた道路でない
この接道義務を満たさない土地では、建物の新築や再建築が認められません。また、市街化調整区域に所在している土地や、建築確認を受けていない建物も再建築不可となるケースがあります。
これらの条件に該当する場合、原則として建物を建て替えられないため、再建築不可物件として売却しなければいけません。
再建築不可物件の売却が難しい理由

再建築不可物件の売却が難しい、他の不動産と比べて難航する理由として、以下の4つが挙げられます。
それぞれの理由について解説していきます。
建て替えができない

再建築不可物件の売却が難しい理由として最も挙げられるのが、建て替えができない点です。
通常、買い手は将来的な建て替えやリノベーションを視野に入れて物件を選びます。しかし、再建築不可物件ではそれができないため、需要が大きく制限されます。
特に老朽化が進んでいる建物の場合、取り壊し後に新たな住宅や施設を建築できないことから、購入希望者にとって利用価値が著しく低くなります。
そのため、再建築不可物件は市場での流動性が低く、売却活動が長期化しやすいという特徴があります。場合によっては、買い手が見つからず売却に至らないケースも珍しくありません。
住宅ローンが利用できない

再建築不可物件は住宅ローンの利用が難しいため、売却が困難になるケースが多く見られます。
金融機関は融資対象とする不動産に対して担保価値を重視しますが、再建築不可物件は将来的な資産価値の維持や流通性が低いため、担保としての評価が著しく下がります。そのため、住宅ローンの審査に通らず、現金での購入が前提となってしまいます。
現金購入を検討できる買主は市場全体の中でも限られていることから、購入希望者の母数が少ないです。売却期間が長引くリスクや、価格交渉において不利な立場に立たされることもあります。
この点を踏まえ、売却活動を行う際は現金購入に強い買取業者に相談するべきです。
修繕費がかさむ

再建築不可物件の売却が難しい理由の一つに、修繕費の負担が大きい点が挙げられます。
再建築不可物件は築年数が古いケースが多く、建物自体が劣化していることが一般的です。しかし、建物を解体して新たに建て替えられないため、既存建物を維持・利用する前提で修繕する必要があります。
その際、屋根・外壁・配管設備などの大規模な修繕を求められる可能性があり、買主にとって大きな負担となります。このような修繕費の見込みがあると、物件購入に対するハードルが高くなり、売却の難易度が上がる要因となるのです。
売却活動を進める際には、修繕費の見積もりを把握して置く必要があります。
用途が限定される

用途が限定される点も、再建築不可物件の売却が難航する原因です。建物の建て替えができないため、購入者は既存の建物をそのまま利用するか、別の目的で土地を活用するしか選択肢がありません。
住宅として使用できるケースもありますが、建物の老朽化が進んでいる場合はリフォーム費用がかさみ、購入をためらう要因となります。また、土地利用についても制約が多く、資材置き場や駐車場など限られた用途しか選べません。
このように再建築不可物件は使い道が制限されるため、購入希望者が集まりにくく、売却までに時間がかかるリスクが高まる点に注意が必要です。
再建築不可物件の売却相場

再建築不可物件の売却相場は、一般的な物件と比較して大幅に低くなる傾向があります。具体的には、物件価格の約3割から7割程度が相場とされていて、建て替えや増築ができないという制約が資産価値を下げてしまいます。
このような価格差は、以下の要因によって変動します。
- 立地条件
- 建物の状態
- 土地の形状
例えば、利便性の高い場所にある物件や、建物の状態が良好である場合は、相場の上限に近い価格での売却が期待できます。一方で、アクセスが悪い場所や老朽化が進んでいる物件は、相場の下限に近い価格、あるいはそれ以下での取引となる可能性があります。
また、再建築不可物件は金融機関からの担保評価が低いため、住宅ローンの利用が難しく、現金での購入を前提とする買主に限定されることが多いです。このような背景から、売却相場は一般的な住宅に比べて低くなると言えるでしょう。
再建築不可物件の売却アプローチ

再建築不可物件の売却を成功させるには、再建築不可物件の特徴に合わせて売却プランを検討する必要があります。具体的には、以下のアプローチ方法があります。
- 再建築を可能にして売却する
- 再建築不可物件のまま売却する
再建築不可物件は、そのまま売却する方法に加え、再建築を可能にしてから売り出す選択肢もあります。再建築を可能とする場合、資産価値を高めて売却できますが、一方で手続きが複雑で手間がかかるといったデメリットも考えられます。
以下では、それぞれの売却方法について解説していきます。
再建築不可物件を売却せず放置するリスクは?
再建築不可物件は「建て替えができない」という制約があるため、売却をためらって放置するケースもあります。しかし、放置すると資産価値の低下や維持費の負担、安全面のリスクなど、所有者に大きなデメリットが発生します。
ここでは放置によって起こり得る代表的な3つのリスクを整理しました。
放置するリスクを理解することは、売却や活用の決断を後押しするきっかけとなるでしょう。以下で詳しく解説します。
資産価値が下がり続ける
再建築不可物件は需要が限られるため、時間が経つほど価値が下がる傾向にあります。築年数の経過や建物の劣化が進むと買い手が見つかりにくく、最終的には大幅な値下げをしないと売却が難しくなるケースもあります。
資産価値の下落を食い止めるには、放置せず早めに売却や活用を検討することが重要です。価値が高いうちに行動することで、経済的損失を最小限に抑えることができます。
固定資産税など維持費の負担が増える
不動産を所有している限り、毎年固定資産税や都市計画税の支払い義務が発生します。特に収益を生まない再建築不可物件は、所有するだけで赤字を生む状態になりやすいのが実情です。
さらに、建物を空き家のまま放置すると雑草や外壁の管理も必要となり、維持費が増加します。収益化できないのに維持コストだけがかかる状況を避けるためには、早めに売却や処分を検討することが望ましいです。
老朽化による安全面や近隣トラブルの懸念
放置された建物は年数が経過するにつれ老朽化が進み、倒壊や屋根・外壁の落下といった危険を招く可能性があります。こうした状況は近隣住民に迷惑をかけ、景観や衛生面でも問題視されやすくなるので注意が必要です。
最悪の場合、自治体から解体や修繕を指導されることもあり、所有者の負担が一層増える恐れがあります。老朽化によるリスクを避けるためにも、長期間の放置は避け、適切な対応を早めに検討することが重要です。
再建築不可物件は早めに売却がおすすめ!
再建築不可物件は早めに売却するのがおすすめです。なぜなら、再建築不可物件は所有を続けるほど建物の老朽化が進み、資産価値が下がる特徴があるからです。
買い手がつきにくくなるだけでなく、固定資産税などの維持費が毎年発生し、所有者にとって大きな負担となります。さらに、倒壊や近隣への被害といった安全面のリスクも増すため、放置するほど売却は困難になります。
価値があるうちに早めに売却すれば、損失を抑えつつ安定した資金化が可能です。専門の不動産業者や訳あり物件に強い買取会社へ相談することで、スムーズに売却を進められる点もメリットといえるでしょう。
再建築を可能にして売却する方法

再建築を可能にして売却する場合、以下のような方法があります。
それぞれの方法について解説していきます。
隣地を取得する

再建築可能にして売却する方法の一つに、隣地を取得する手段があります。
建築基準法に満たしていない場合でも、隣接する土地を取得して接道義務を果たせば、再建築が可能です。隣地の所有者と交渉し、必要な部分を購入または譲り受けることで、法的要件をクリアし、物件の資産価値を大きく高めることが可能になります。
ただし、隣地所有者との交渉は簡単ではなく、価格や条件面で折り合う必要があるため、専門家を交えて慎重に進めることが推奨されます。
再建築不可物件を再建築可能にするのは最も代表的な方法ですが、これによって売却価格の大幅な向上が見込めます。
セットバック

セットバックとは、現状の道路幅が建築基準法に定める4メートルに満たない場合に、敷地の一部を道路用地として後退させることを指します。この措置により、接道義務をクリアできる可能性が生まれ、建物の再建築が許可されるケースがあります。
セットバックを行う場合、後退した部分は道路とみなされるため、建築可能な敷地面積が減少する点に注意が必要です。しかし、再建築が可能となれば資産価値は高まり、売却活動も格段に有利に進めることが可能です。
そのためには、事前に役所で接道状況を確認し、具体的な対応策を検討するようにしましょう。
接道部分を位置指定道路の認定を受ける

再建築不可物件でも、接道部分を位置指定道路として認定を受けることで、再建築可能にできる場合があります。
位置指定道路とは、建築基準法第42条に基づき、一定の基準を満たした私道を自治体が道路として認めたものを指します。認定を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 道路幅員が4メートル以上
- 道路が公衆用に利用されている
- 周辺関係者の同意を得る
申請手続きには測量や図面作成、関係者との調整が伴うため、一定の時間と費用を要します。ただし、認定されれば再建築が可能となり、売却価格の大幅な向上が期待できるでしょう。
「接道義務の特例許可」を申請する

再建築不可物件は、「接道義務の特例許可」を申請することで再建築が可能となる場合があります。この特例は建築基準法第43条の規定に基づき、特定行政庁が個別に判断して認める制度です。
具体的には、安全上支障がないと認められる場合に限り、幅員の不足する道路に接する土地であっても再建築が許可されます。ただし、必ずしも許可が下りるわけではなく、以下のような条件が厳しく審査されます。
- 周辺環境
- 避難経路の確保状況
- 既存建物の状況
そのため、行政や専門家に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。許可が取得できれば、物件の魅力が高まって買主の層も広がるため、売却の成功確率が向上します。
再建築不可物件のまま売却する方法

再建築不可物件をそのまま売却する場合は、以下のような方法が有効です。
それぞれの方法について解説していきます。
再建築不可であることを伝える

再建築不可物件をそのまま売却する場合、再建築不可である事実を買主に伝えることが重要です。
売主には宅地建物取引業法に基づく告知義務があり、これを怠るとトラブルに発展するリスクがあります。買主に対して、建て替えができない理由や現行法における制約内容を説明し、納得した上で購入判断をしてもらうことが大切です。
再建築不可であることを隠さないことは、むしろ信頼性を高めることになるでしょう。適切な情報開示を行えば、投資家や事業者にリーチでき、スムーズな売却につながる可能性が高まります。
再建築不可であることを含め、物件の状況はしっかりと伝えましょう。
物件の活用可能性を提案する

再建築不可物件をそのまま売却する際には、物件の活用可能性を提案するのが有効です。再建築不可物件では建て替えができない制約を補うため、以下のような活用方法を提案することで、買主は購入に前向きになりやすくなります。
- 現存建物をリフォームして賃貸物件とする
- 土地を駐車場にする
- 資材置き場として利用する
- 事務所やアトリエ
このような用途に適しているポイントをアピールすることで、購入検討者の幅を広げることが可能です。
物件の特性に合わせた活用提案は、買主にとって収益性・利便性をイメージしやすくするため、購入意欲を高める要素となります。売却活動にあたっては、これらの活用案を広告や内覧時に丁寧に伝えましょう。
隣地所有者への売却を検討する

隣地所有者への売却を検討するのも、再建築不可物件のまま売る方法として有効です。隣接する土地の所有者にとって、再建築不可物件は土地の間口を広げ、接道義務を満たす手段となる可能性があるため、魅力的な提案となり得ます。
隣地と一体化することで再建築が可能になるケースでは、相手側も積極的に購入を検討してくれます。ただし、隣地所有者にとって必ずしも必要な土地とは限らないため、交渉には慎重なアプローチが必要です。
事前に用途や意向を確認し、適正な価格設定を行うことが重要です。交渉が成立すれば、一般市場に売却するよりも早期に売却できる可能性があります。
リフォーム・リノベーションを行う

リフォームやリノベーションを行うことで、再建築不可物件のままでも売却することが可能です。建物自体は再建築できなくても、一定範囲内の修繕や改修は認められているため、内外装を整えることで物件の魅力を高められます。
特に、以下のような工事を実施するのが効果的です。
- 水回りの設備更新
- 外壁の修繕
- 間取りの改善
リフォームによって「住める状態」であることをアピールできれば、自宅用や収益物件としての購入ニーズを引き出しやすくなります。
ただし、過度な費用をかけると採算が取れないリスクもあるため、必要最低限の工事内容を見極めることが大切です。費用対効果を考慮して改修を行い、訴求ポイントを明確に打ち出すことが重要になります。
再建築不可物件を売却する際の注意点
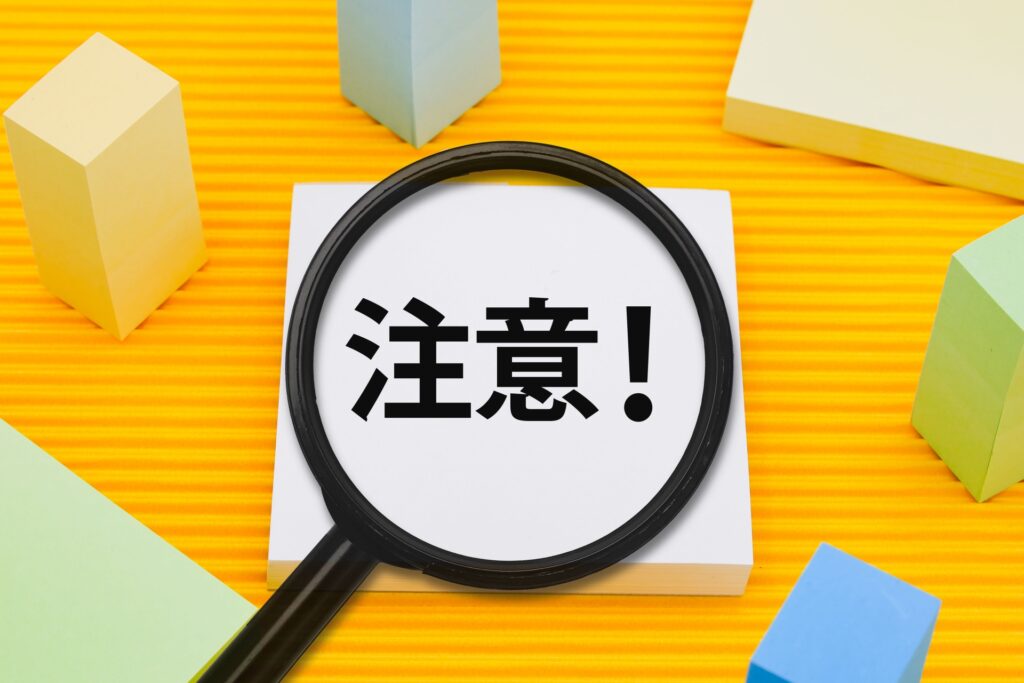
再建築不可物件を売却する過程では、以下の点に注意して進めることが重要です。
それぞれの注意点について解説していきます。
建物は解体せず残しておく

再建築不可物件を売却する際は、建物を解体せず残しておくようにしましょう。建物を解体してしまうと、建築基準法により新たな建物を建築できず、単なる更地となってしまいます。
建物が存在している状態であれば、たとえ老朽化していてもリフォームや用途変更による活用の余地があり、購入希望者の選択肢を広げることが可能です。
賃貸物件や倉庫利用を検討する投資家にとっては、現存する建物を生かせることがメリットとなるため、解体せず売却したほうが成約の可能性を高めります。
解体して土地の状態で売り出したいと思うかもしれませんが、解体はしない方針で進めるのがおすすめです。
売主の判断でリフォームを行わない

再建築不可物件を売却する場合、売主の判断だけでリフォームを行わないように注意しましょう。見た目を整えれば売却しやすくなると考えがちですが、買主が求める改修内容や用途はそれぞれ異なります。
そのため、売主側の一方的な判断でリフォームを施しても、かえって購入希望者のニーズに合わず敬遠されるかもしれません。また、リフォーム費用を上乗せした価格設定が原因で、売却までに時間がかかるケースも少なくありません。
そのため、物件の現況を伝えたうえで、買主自身が改修プランを立てられるよう配慮することが望ましいです。売却を成立させるためには、買主の購買意欲が不可欠です。
「こうすれば売れるだろう」と判断するのではなく、交渉しながらリフォームを検討しましょう。
売却までに時間がかかる

再建築不可物件の売却は、通常の不動産に比べて時間がかかります。再建築不可という制約は、購入希望者の選択肢を制限するため、買い手が見つかりにくくなります。
また、金融機関からの融資が受けにくいことも、購入者が限られる要因となり、結果的に売却期間の長期化を招くでしょう。建物の老朽化や土地利用が限定されることで、買主は購入判断に慎重になる傾向が強まるため、交渉にも時間がかかります。
再建築不可物件の売却では、早期売却を目指す場合であっても、一定期間の余裕を持って計画を立てることが重要です。焦ることなく、確実に売却できるように準備しましょう。
買取や訳あり物件に強い業者に依頼する

再建築不可物件の売却では、買取や訳あり物件に強い不動産業者に依頼するのがおすすめです。通常の不動産会社では、再建築不可物件の取引事例が少ないため、売却が長引く、もしくは売却できない可能性もあります。
一方で、買取や訳あり物件に強い会社は、再建築不可物件のリスクや活用方法に精通しており、価格査定や早期売却をサポートしてくれます。
また、売主側にとっての手続き負担が軽減されるメリットもあります。信頼できる業者を選ぶ際は、過去の実績や口コミを十分に確認し、複数社から比較検討することが重要です。
再建築不可物件を売却する際によくある質問!Q&A
再建築不可物件を初めて売却しようとすると、「売れるのか?」「価格は?」など基本的な疑問が多く出てきます。
ここでは、初心者の方が不安に感じやすい代表的な質問をまとめて、一問一答形式でわかりやすく解説します。
再建築不可物件でも本当に売れるの?
はい、売却は可能です。ただし買い手は限られており、一般の購入希望者よりも隣地所有者や専門業者への売却が中心になります。仲介だけでなく買取も選択肢です。
普通の家よりも売却価格は安くなるの?
再建築できない制約があるため、一般的な住宅より価格は下がる傾向があります。立地や需要によりますが、相場の7割以下になることもあります。
住宅ローンが残っていても売却できる?
売却自体は可能ですが、売却代金で残債を完済する必要があります。完済できない場合は金融機関と相談して任意売却を検討する方法もあります。
解体して更地にした方が売れやすい?
更地にしても「再建築不可」という条件は変わりません。場合によっては建物を残したまま、リフォーム提案など活用方法を示した方が売却につながることもあります。
売却するのにどのくらい時間がかかる?
需要が少ないため、通常の物件より時間がかかることが多いです。数か月から半年以上かかるケースもありますが、専門業者への買取なら早期売却が可能です。
どんな不動産会社に依頼すればいい?
再建築不可や訳あり物件の売却に実績がある会社を選ぶことが大切です。一般的な不動産会社では対応が難しい場合もあるため、専門業者や買取実績のある会社がおすすめです。
西湘エリアでの再建築不可物件の買取はハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめ

再建築不可物件の売却において、西湘エリアで信頼できる業者をお探しの方には、ハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | ハウスドゥ 小田原市役所前 |
| 会社名 | 株式会社Forest field |
| 所在地 | 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪531-6 |
| 電話番号 | 0465-34-2555 |
| 公式HP | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/satei/ |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31148号 |
同社は小田原市を中心に、南足柄市や箱根町など西湘地域に密着した不動産サービスを展開しています。再建築不可物件に加え、築古物件や相続物件など、他社では対応が難しいとされる物件の買取実績が豊富です。
全国展開するハウスドゥのフランチャイズに加盟しており、豊富なノウハウと確かな信頼性を備えています。無料査定や丁寧なヒアリングを通じて、個々の事情に応じた最適な提案を行っており、迅速な手続きと親身な対応が強みです。
再建築不可物件の売却を検討されている方は、ハウスドゥ 小田原市役所前に相談してみてください。
また、ハウスドゥ 小田原市役所前の空き家買取や不動産売却について気になる方はお問い合わせしてみてください。
まとめ

再建築不可物件は一般的に売却が難しいとされていますが、不可能ではありません。再建築不可物件のままでも可能ですし、再建築を可能にしてから売却することも可能です。
ただし、再建築不可物件の売却が難しいことには変わりません。そのため、買取や訳あり物件に強い業者に依頼して、売却をサポートしてもらうことをおすすめします。専門家に相談することで、売却の成功確率は格段に高まります。
再建築不可物件は売れないとあきらめずに、時間をかけて売却を目指しましょう。