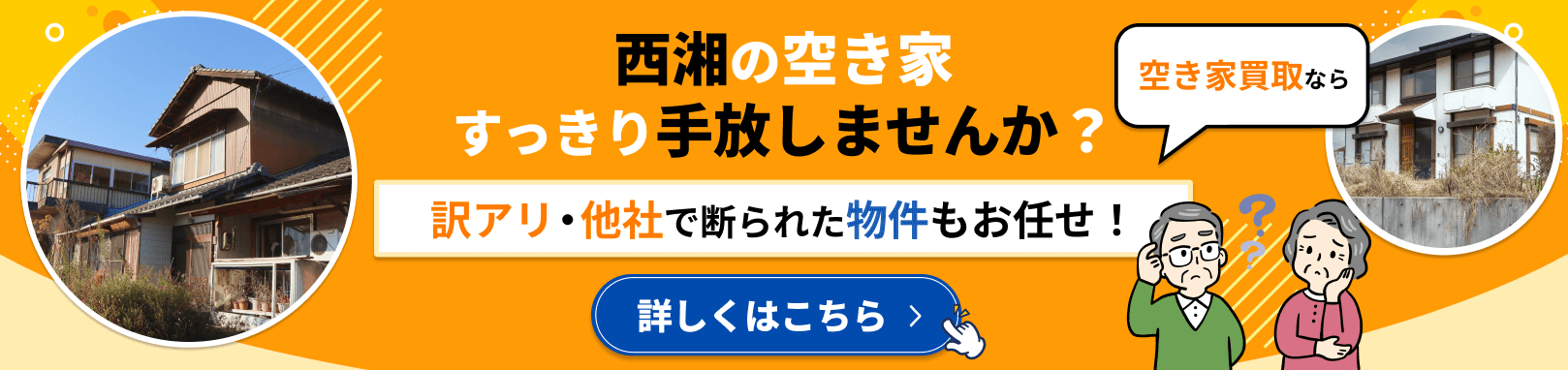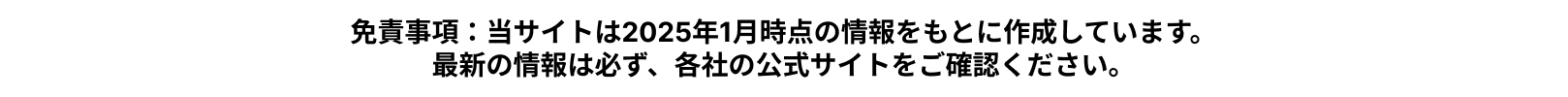相続人がいない空き家は、適切な管理や処分が難しく、地域の課題となっています。2024年の民法改正により、所有者不明土地・建物の管理制度が創設され、新たな解決方法も整備されました。
本記事では、相続人不在の空き家はどうしたらいいのか、対処法や放置するリスク、所有者責任や売却方法まで詳しく解説します。空き家問題でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、以下の記事では、西湘エリアの空き家について触れているサイトなので、参考にしてみてください。
相続人がいない空き家はどうすればいい?

相続人がいない空き家は、所有者不明のまま放置されるケースが多く、老朽化や倒壊、近隣トラブルの原因となりやすい問題です。特に高齢化や単身世帯の増加により、今後このような空き家が全国的に増えると見込まれています。
放置しておくと行政の管理下に置かれたり、固定資産税の軽減措置が外れるなどの不利益を受ける可能性もあります。そのため、早めに法的な手続きを踏んで対応することが重要です。
相続人がいない空き家を放置するとどうなる?

相続人がいない空き家を長期間放置してしまうと、老朽化による倒壊の危険性や近隣トラブル、税負担の増加など、さまざまな問題が発生します。特に、所有者が不明な状態では修繕や管理が行われないため、放置すればするほど状況は悪化していきます。
ここでは、相続人不在の空き家を放置した場合に起こり得る主なリスクを整理して解説します。
空き家を放置することは、単なる管理の問題にとどまらず、法的・経済的な負担にもつながります。それぞれのリスクを詳しく確認していきましょう。
老朽化・倒壊による安全リスク
人が住まなくなった空き家は、風通しやメンテナンスが行われないことで急速に老朽化が進みます。木材の腐食、屋根の破損、外壁の崩落などが起こると、通行人や隣家への被害を引き起こす可能性があるので注意が必要です。
実際に全国で空き家の倒壊事故が報告されており、所有者不明のまま放置された建物は特に危険視されています。
また、害虫の発生や雑草の繁茂など、衛生面の問題も深刻です。これらのリスクを防ぐためには、早期の対応が不可欠です。
行政代執行や固定資産税の増加
老朽化が進んだ空き家は、自治体による調査や指導の対象になります。改善命令に従わず放置を続けた場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、行政代執行として強制的に解体されることがあるので注意が必要です。その際の費用は所有者または相続財産から徴収される仕組みです。
また、特定空き家に指定されると固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が最大6倍に増えるケースもあります。行政による措置は、放置への警鐘として厳格に運用されています。
特定空き家に指定される可能性
相続人がいない空き家を放置すると、外観の損壊や周囲への危険性から「特定空き家」に指定されることがあります。
特定空き家とは、倒壊や衛生被害の恐れがあるなど、周辺環境に悪影響を及ぼすと判断された物件を指します。一度指定されると、自治体から改善命令が出され、対応しなければ行政代執行による解体処分を受ける可能性があるので注意が必要です。
さらに、固定資産税の優遇が解除されるなど経済的な負担も発生します。空き家を安全かつ適正に管理することが、指定回避の唯一の方法です。
相続人がいない空き家の対処方法

相続人がいない空き家の対処には、法制度に基づいた適切な手続きが必要です。2024年の法改正により、新たな制度も整備され、より実効性のある対応が可能となっています。ここでは、具体的な対処方法について解説します。
以下で詳しく解説します。
特別措置法による対応
空家等対策特別措置法では、管理不全の空き家に対して行政が取れる措置が定められています。特に危険な「特定空家等」に認定された場合、行政は所有者等に対して、除却や修繕などの勧告・命令を行うことができます。
また、緊急時には行政代執行による強制的な措置も可能です。具体的な措置としては、建物の解体・撤去、樹木の伐採、害虫の駆除などが含まれます。これらの措置にかかる費用は、本来所有者が負担すべきものですが、相続人不在の場合は、財産管理人制度と組み合わせて対応することになります。
相続財産管理人制度の活用
相続人がいない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任することができます。この制度は、相続人不在の財産を適切に管理・処分するために設けられています。
相続財産管理人には通常、弁護士や司法書士が選任され、相続財産の調査、債権者への弁済、残余財産の国庫帰属などの手続きを行います。特に空き家の場合、建物の売却や解体などの処分方法を検討し、実行することが主な業務となります。
所有者不明土地管理制度
2024年の民法改正で創設された所有者不明土地管理制度は、相続人不在の空き家問題に新たな解決策を提供します。この制度では、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、所有者不明の土地・建物を適切に管理・処分することが可能となりました。従来の相続財産管理人制度と比べ、手続きが簡素化され、費用面でも効率的な対応が可能です。
具体的には、管理人による建物の修繕や売却、場合によっては解体まで行うことができ、地域の課題解決に向けた実効性の高い制度として期待されています。
具体的な解決までの流れ

相続人がいない空き家の問題を解決するためには、法的手続きと実務的な対応を適切に組み合わせる必要があります。まずは相続人の有無を確実に調査し、その結果に基づいて具体的な対応を進めていきます。
ここでは、解決までの具体的な流れを解説します。
以下で詳しく解説します。
相続人調査の方法
相続人の調査は、戸籍謄本の収集から始まります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、法定相続人の有無を確認します。調査には、以下の手順で進めることが重要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
- 配偶者・子の有無の確認
- 親・兄弟姉妹の調査
- 相続放棄の有無の確認
- 戸籍の追跡が困難な場合の公告手続き
手順を守って調査する必要があります。
財産管理人選任の手続き
相続人不在が確認された場合、財産管理人の選任申立てを行います。この手続きは、利害関係人(近隣住民、自治体、債権者など)が家庭裁判所に対して行います。申立てには、相続人不在を証明する戸籍関係の書類や、対象となる空き家の登記事項証明書、固定資産評価証明書などが必要です。
申立てが認められると、裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を財産管理人として選任します。選任後は、官報公告による相続人や債権者の探索が行われ、通常2~3ヶ月の期間を要します。
売却・解体までの手順
財産管理人が選任されると、具体的な財産の処分手続きが始まります。まず財産管理人は、空き家の現状調査と評価を行い、最適な処分方法を検討します。売却が可能な場合は、不動産業者への媒介依頼や買主の募集を行います。
解体が必要な場合は、解体業者の選定と工事の実施を進めます。これらの手続きには裁判所の許可が必要となりますが、所有者不明土地管理制度を利用する場合は、より柔軟な対応が可能です。処分によって得られた金銭は、債務の弁済に充てられ、残余財産は最終的に国庫に帰属することになります。
また、以下の記事では空き家解体の費用について書いているので参考にしてみてください。
相続人がいない空き家の所有者責任はどうなる?

相続人がいない空き家は、誰が管理すべきなのか、事故や損害が発生した場合に誰が責任を負うのかが不明確になりやすい問題です。
所有者が死亡した後も、相続手続きがされていなければ法的な管理者が存在しないため、地域社会に悪影響を及ぼすケースが増えています。
放置すれば、老朽化による倒壊や火災、近隣トラブルなどを引き起こす可能性があり、行政が介入せざるを得ない事態に発展することもあります。こうしたトラブルを防ぐには、相続人不在の空き家の「所有者責任」がどのように扱われるのかを正しく理解することが重要です。
主なポイントは次のとおりです。
・所有者不明でも管理義務は残る
・行政や裁判所が関与して管理を行う場合がある
・近隣トラブルに発展するリスクがある
相続人がいない空き家は、形式上の所有者がいなくても「管理責任が消えるわけではない」と法律上定められています。倒壊などで第三者に被害が出た場合、相続財産から損害賠償が行われる可能性もあるので注意が必要です。
また、空家等対策特別措置法に基づき、自治体が「特定空き家」として調査や勧告を行うこともあります。さらに、放置された建物が原因で火災や害虫被害が起きると、近隣との関係悪化にもつながります。
管理人の選任や行政対応を通じて、早期に責任の所在を明確にしておくことが大切です。
相続人不在の空き家を売却することはできる?

「相続人がいない空き家は売れないのでは?」と思われがちですが、実は法的な手続きを踏めば売却が可能です。
相続人が存在しない場合でも、家庭裁判所に申し立てを行い「相続財産管理人」を選任してもらうことで、空き家を売却し、資産を適正に処分できます。
この制度は、放置された空き家を市場に戻すことで地域の安全や土地活用を促すために整備されたものです。手続きには時間がかかりますが、法的な流れを理解しておけば安心して進めることができます。
売却の流れは以下のとおりです。
・相続財産管理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう
・裁判所の許可を得て空き家を売却する
・売却代金は債務や経費を精算後、国庫に帰属する
まず、相続人不在の場合は家庭裁判所が管理人を選任し、裁判所の監督下で空き家の査定・売却が行われます。売却代金は、未払い税金や債務の支払いに充てられ、残額があれば最終的に国庫へ納められます。
こうした法的手続きを経ることで、所有者がいない空き家でも安全かつ適正に処分できます。売却によって老朽化した建物の放置を防ぎ、地域環境の改善にもつながる重要な制度です。
空き家を売却するなら、信頼できる不動産会社に依頼しよう!

空き家を売却する際は、手続きの複雑さや法律面の確認、適正な価格設定など、個人だけで進めるには多くの課題があります。特に相続や老朽化した空き家の場合、権利関係や建物の状態が複雑になりやすいため、専門的な知識を持つ不動産会社のサポートが不可欠です。
信頼できる不動産会社に依頼することで、法的トラブルの回避やスムーズな売却が実現します。ここでは、依頼する際に意識すべきポイントを整理して紹介します。
依頼時に確認すべき主なポイントは次の3つです。
・空き家や相続不動産の売却実績があるか
・査定・説明が丁寧で透明性があるか
・売却後のサポート体制が整っているか
まず、不動産会社を選ぶ際は、空き家売却や相続案件の取り扱い経験が豊富な会社を選ぶことが重要です。経験が多い会社は、登記・税務・リフォーム対応など幅広い知識を持っており、複雑な手続きを的確に進められます。
さらに、査定内容や手数料などを明確に説明してくれる会社は信頼性が高く、安心して取引を任せられます。売却後のアフターフォロー体制が整っているかも重要な判断基準です。これらの点を比較・検討することで、納得のいく売却を実現できるでしょう。
西湘エリアの空き家買取はハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめ

西湘エリアで相続人不在の空き家の処分をお考えの方に、特におすすめなのがハウスドゥ 小田原市役所前です。財産管理人制度を活用した空き家の買取実績があり、弁護士や司法書士との連携により、スムーズな解決をサポートします。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | ハウスドゥ 小田原市役所前 |
| 会社名 | 株式会社Forest field |
| 所在地 | 〒250-0042 神奈川県小田原市荻窪531-6 |
| 電話番号 | 0465-34-2555 |
| 公式HP | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/satei/ |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31148号 |
また、相続人不在物件特有の複雑な手続きにも精通しており、適切なアドバイスを提供できます。
ハウスドゥ 小田原市役所前は、相続人不在の空き家問題に対して、包括的な解決支援を提供しています。財産管理人との連携により、適切な価格での買取を実現し、近隣への影響を最小限に抑えた解体・処分も可能です。
また、行政との調整や必要な手続きのサポートも行っており、地域の空き家問題解決に貢献しています。ご相談は無料で承っておりますので、空き家でお困りの方は、まずはお気軽にご連絡ください。
また、ハウスドゥ 小田原市役所前の空き家買取や不動産売却について気になる方はお問い合わせしてみてください。
なお、次の記事では空き家解体費用の相場と対策を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

まとめ
相続人がいない空き家の問題は、適切な手続きと専門家の支援により、解決が可能です。近年の法制度の整備により、より実効性の高い対応が可能となっていますが、早期の対策が重要となります。
以下のポイントを押さえて対応することをお勧めします。
- できるだけ早い段階での相続人調査の実施
- 必要に応じた財産管理人選任の検討
- 行政や専門家への相談による適切な対応
- 地域への影響を考慮した迅速な処理
特に西湘エリアでは、ハウスドゥ 小田原市役所前が相続人不在の空き家問題に関する豊富な経験と実績を持っています。「このまま放置してよいのかわからない」「どこに相談したらよいかわからない」という場合は、まずは気軽に相談することをお勧めします。
相続人不在の空き家は、放置すればするほど問題が複雑化する傾向にあります。できるだけ早い段階での対応を心がけ、適切な解決方法を見つけることが重要です。Forest fieldでは、空き家に関する無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。