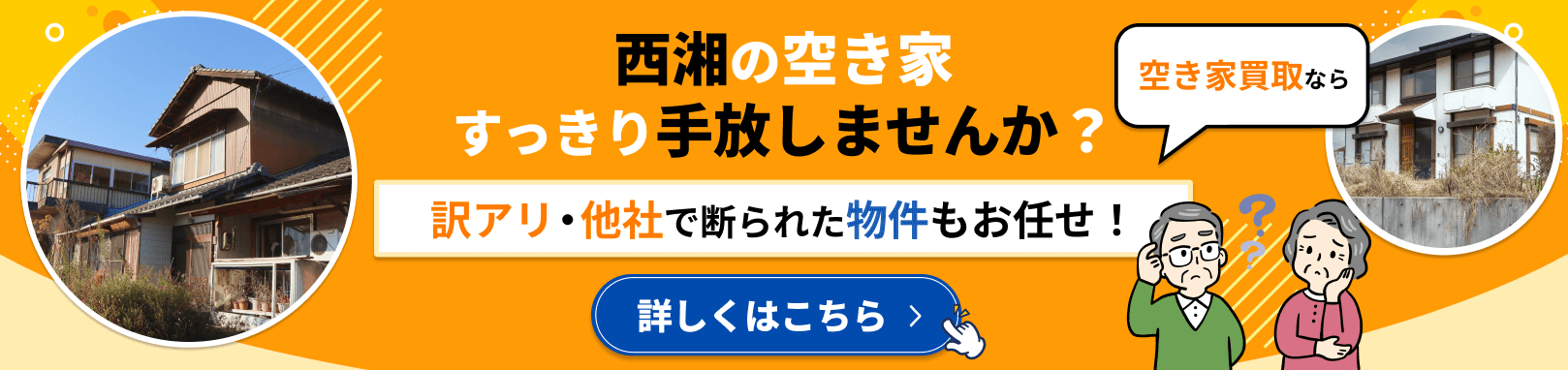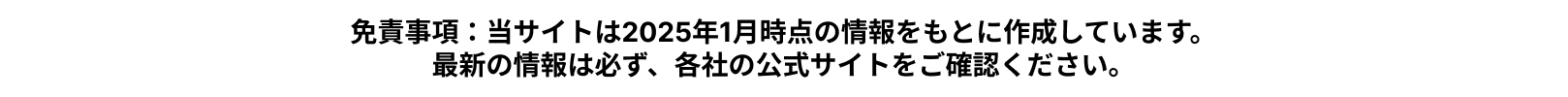空き家を所有する場合、火災保険が適用されるのか気になる方も多いでしょう。人が住んでいない空き家が火災保険に加入することは可能なのか、空き家を所有する方は知っておく必要があります。
空き家は一般的な住宅と比べて、火災保険への加入条件が厳しく設定されています。また、保険料が高額になるリスクもあるため、加入条件や手続きの進め方、さらには保険料を抑えるポイントについて理解しておくことが重要です。
この記事では、空き家の火災保険が適用される条件や必要な手続き、加入時の注意点について解説していきます。空き家を所有していて、今後どうするか決めていない方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下の記事では、西湘エリアの空き家について触れているサイトなので、参考にしてみてください。
火災保険の必要性

空き家であっても、火災保険への加入は極めて重要です。
空き家は人が常時出入りしないため、火災が発生した場合に発見や初期消火が遅れるリスクが高まります。また、不審火や放火といった第三者による被害も起こりやすく、被害が拡大しやすい傾向にあります。
万が一、隣家など周囲の建物に被害を及ぼした場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性も否定できません。このようなリスクに備えるため、空き家であっても火災保険に加入しておくことが、資産を守る上で欠かせない対策となります。
また、火災保険は風災・水災といった自然災害に対する補償も組み込める場合があり、リスクを幅広くカバーすることが可能です。
空き家に火災のリスクはある?

人が済まない空き家であっても、火災リスクは確実に存在します。人の目が届かない時間が長いと、以下のリスクがあります。
- 漏電による火災
- 不審者による放火
特に老朽化した建物は電気設備や配線が劣化していることが多く、わずかな異常が原因で火災につながる恐れがあります。また、空き家は雑草や廃材が放置されやすく、これらが燃え広がる原因になることもあります。
さらに、誰も住んでいないことを知った上での放火被害も全国で報告されており、社会問題にもなっています。このように空き家は火災リスクが高く、適切な管理と対策を講じなければ深刻な被害を招くことになるのです。
火災保険に加入できる空き家の条件
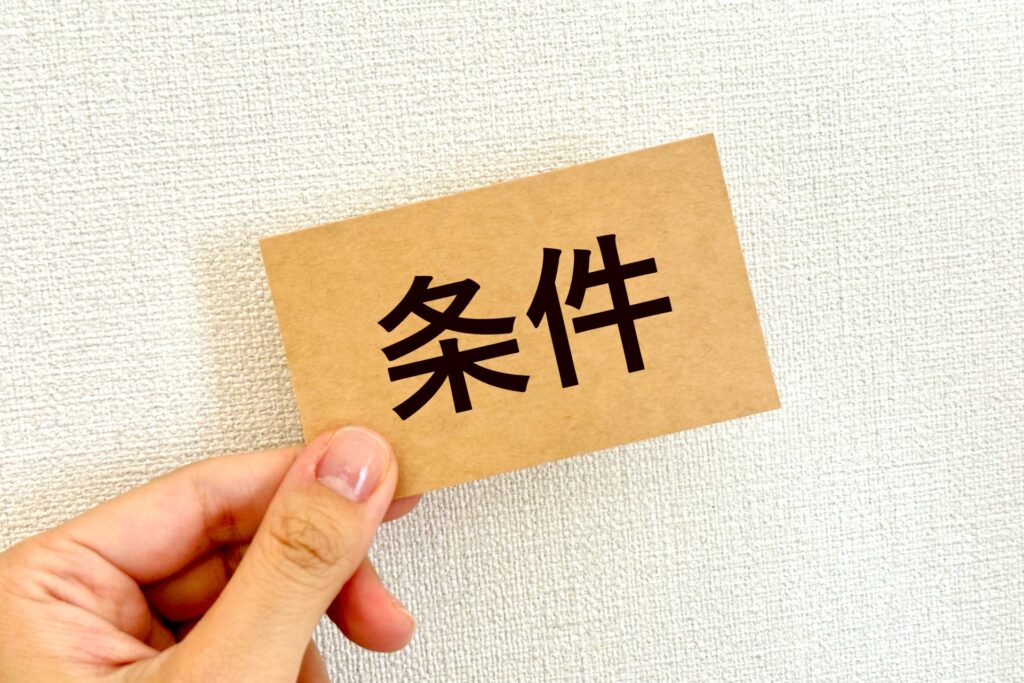
人が住んでいない空き家が火災保険に加入するには、一般の住宅とは異なり、以下の条件をクリアしなければいけません。
それぞれの条件について解説していきます。
1.定期的な管理・点検がされている

空き家が火災保険に加入するためには、定期的な管理・点検が行われていることが重要な条件の一つとなります。
保険会社は火災リスクを適切に抑制できるかを重視しており、長期間放置された空き家については、加入を断られる可能性があります。具体的には、以下のような作業が適切に実施されているかが判断基準となります。
- 建物の内部・外部の点検
- 雑草の除去
- ゴミの清掃
- 破損箇所の修繕
これにより、漏電や不審火などの発生リスクを低減できると評価され、保険契約の承認につながります。逆に、管理が行き届いていないと、火災だけでなく倒壊や第三者への損害賠償リスクも高まるため、保険会社に敬遠される場合も少なくありません。
2.建物の劣化状況が著しくない

空き家でも火災保険に加入することは可能ですが、そのためには建物の劣化状況が著しくないことが条件となります。
保険会社は契約時に、建物の安全性や保全状況を確認します。その際に、老朽化が進み損壊のリスクが高い物件については、引受を拒否したり補償範囲を制限したりする場合があります。
たとえば以下の状態が見受けられる場合、保険金支払いリスクが高まると判断されるため注意が必要です。
- 屋根材の破損
- 外壁のひび割れ
- 雨漏り
また、内装や配線設備の劣化も火災リスクと見なされ、契約に支障をきたすでしょう。加入を希望する場合には、建物の管理状態を良好に保つことが求められます。
3.今後住む予定がない

火災保険に加入できる空き家の条件の1つとして、今後住む予定がないことが挙げられます。保険会社はリスク管理の観点から、空き家の状態や使用予定を細かく確認するだけでなく、所有者が今後空き家を利用するかも検討します。
将来的に住居として再利用する計画がない場合、建物の維持管理が不十分になりやすく、火災や損壊リスクが高まると判断される傾向があります。その場合、通常の住宅用火災保険ではなく、空き家専用の火災保険を提案されることが一般的です。
特に、空き家の早期売却・解体を検討しているケースでは、空き家専用保険への加入が必要となります。住む予定がないと明確に説明することで、適切な補償内容や保険料設定が行われ、万一の火災リスクに備える体制を整えることが可能です。
4.放火・盗難などへの対策が取られている

空き家が火災保険に加入するためには、放火や盗難への対策が取られていなければいけません。無人の建物は第三者による侵入や放火の標的になりやすく、リスク管理の観点から、一定の防犯対策が求められる傾向があります。
具体的には、以下のようなものが有効です。こうした対策が確認できると、審査を通りやすくなります。
- 玄関や窓の施錠ができる
- 防犯カメラやセンサーライトの設置
- 敷地内の雑草やゴミの整理
これらの対策が講じられていない場合、火災保険の引き受けを断られるか、保険料が割高になるリスクが高いです。空き家でも適切な管理を実施し、放火や盗難リスクを最小限に抑えることが、保険加入への重要な要件となっています。
空き家に適した火災保険の選び方

空き家を火災保険に加入させる場合、「空き家向け」の保険を選ぶことが重要です。空き家に適した火災保険の選び方は、以下の5つです。
それぞれの選び方について解説していきます。
「空き家向け」または「非居住物件向け」の保険を選ぶ

空き家に火災保険をかける際は、「空き家向け」や「非居住物件向け」と明記された保険を選ぶことが重要です。
通常の住宅用火災保険は、居住者が常に生活している前提で設計されているため、空き家に対しては補償の対象外となる場合があります。そのため、誤って一般の住宅用保険に加入してしまうと、万が一の火災が発生しても保険金が支払われないかもしれません。
一方で空き家向けの保険は、人の不在を前提とした補償内容となっていて、放火や自然災害への備えが強化されているケースが多く見られます。
保険会社によっては、空き家の管理状況に応じて引受可否や保険料が変動するケースもあるため、事前に条件を確認してから選びましょう。
建物の築年数・管理状況に対応している

空き家の火災保険選びでは、建物の築年数や管理状況に対応している保険商品を選ぶことがポイントです。老朽化が進んだ空き家では、火災や倒壊のリスクが高くなるため、保険会社によっては補償内容が制限される場合ケースもあります。
そのため、築年数が古くても加入できる商品や、定期的な管理が行われていることを条件に補償範囲が広がる保険を選ぶことが有効です。
また、外観や設備の維持状況を写真などで提示し、適切に管理されていることを証明できれば、保険料が抑えられることもあります。建物の状態や管理状況が基準となる火災保険を選ぶことが、空き家特有のリスクに備える上で必要な対策です。
免責金額や保険金額の設定

免責金額とは、保険金が支払われる際に自己負担とする金額であり、この額を高めに設定すれば保険料を抑えることができます。
ただし、被害が軽微な場合では保険金が支払われない可能性があるため、リスク許容度に応じた調整が必要です。空き家の築年数を基準に、無理のない範囲で設定するようにしましょう。
一方、保険金額は火災や自然災害による損害に備えて補償される金額であり、建物の再建費用や立地の危険度を基準に設定します。空き家の場合、再建を前提としないケースも多く、その分保険金額を低くすることで保険料を合理的に抑えることが可能です。
これらの設定を適切に行うことで、無駄がなく空き家の状況に最適な火災保険を選べるでしょう。
補償範囲が必要最低限に設定されている

空き家に火災保険を適用する際は、補償範囲が必要最低限に設定されたプランを選ぶことが重要です。居住用住宅と異なり、空き家では家財が存在しない、または最小限であるケースが多く、すべての補償を付帯する必要はありません。
そのため、火災に関する補償だけが盛り込まれた商品に絞ることで、無駄な保険料を抑えることが可能です。逆に、水漏れや盗難など不要な補償を除外することで、保険料の最適化が図れます。
また、補償対象を建物本体に限定することで、リスクに見合った保険設計がしやすくなります。保険会社によっては空き家専用の火災保険を用意している場合もあるため、複数の保険商品を比較し、コストと補償内容のバランスを考慮することが必要です。
保険会社の空き家対応実績を確認する

空き家に適した火災保険を選ぶ際には、保険会社が空き家の対応実績を持っているかも確認しましょう。一般の住宅と異なり、空き家には火災や放火のリスクに加え、風災・老朽化に伴う損傷など特有のリスクが存在します。
そのため、これらのリスクを十分に理解し、適切な補償内容を提案できる保険会社を選ぶことが、後のトラブル回避に繋がります。実績がある保険会社であれば、審査基準や必要な管理状況、補償内容について明確な説明が期待でき、安心して契約に進めます。
保険会社を選ぶ際は、口コミや比較サイト、専門業者への相談を通じて、空き家への補償事例や対応姿勢をチェックしてから依頼するようにしましょう。
空き家の火災保険加入時の注意点

空き家の火災保険加入時には、以下のような注意が必要です。これらに気を付けないと、加入が断られる可能性があります。
それぞれの注意点について解説していきます。
空き家であることを申告する

空き家に火災保険を契約する際には、必ず「空き家であること」を申告しましょう。居住用住宅と比較して、空き家は火災や損壊のリスクが高いため、保険会社はリスクの性質に応じた条件を基準として、契約するかどうかを判断します。
そのため、もし空き家であることを告げずに居住用として契約した場合、いざ事故が発生しても補償が受けられない、あるいは保険契約自体が無効となる可能性があります。
火災保険の中には、保険料や補償範囲が空き家に特化したプランが用意されているため、正直に申告すればそれに適した火災保険に加入できます。
空き家であること、どんな状況なのかを伝えた上で契約内容を決定することで、予期せぬトラブルを未然に防ぐことが可能です。
居住用住宅よりも加入条件は厳しい
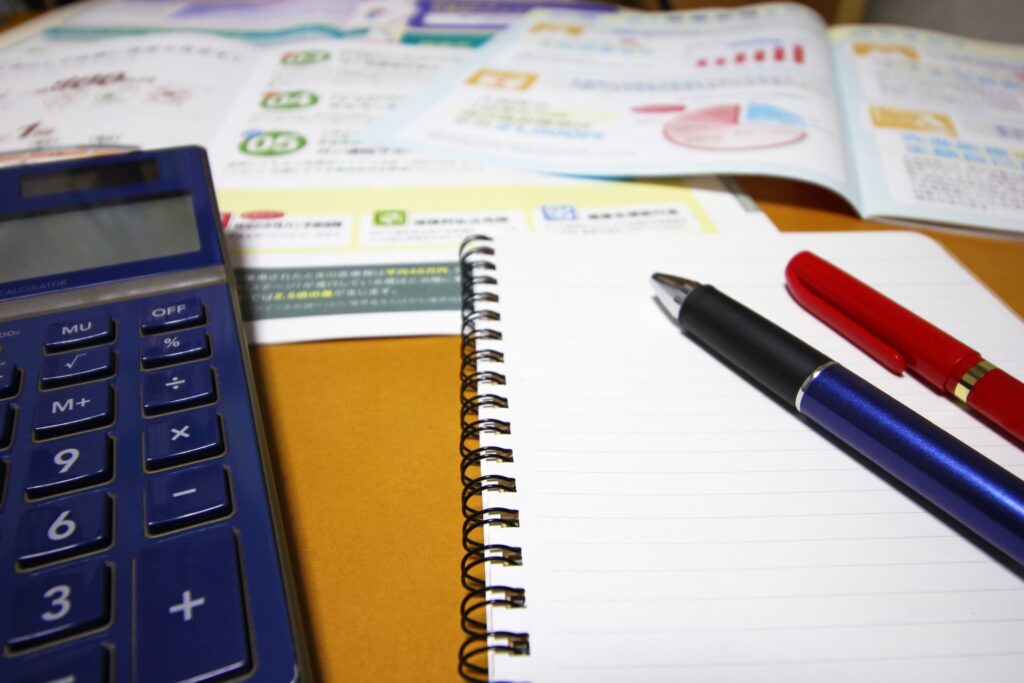
空き家に火災保険をかける場合、居住用住宅と比較して加入条件が厳しく設定される点に注意が必要です。空き家は人の目が行き届かないため、火災や放火による被害が発見されるまでに時間がかかり、被害が拡大するリスクが高いと見なされます。
そのため、保険会社は通常よりも厳しい管理状況や防犯対策を求める傾向にあり、一定の防火措置や定期的な点検の実施が条件とされることもあります。
加えて、建物の老朽化具合によっては、保険料が高額になったり、引き受け自体を断られるケースも考えられるでしょう。
空き家に対する火災保険を検討する際は、事前に加入条件を確認し、必要な対策を講じることが重要です。ある程度の時間がかかることは覚悟しておきましょう。
放置したままだと加入できない可能性がある

建物を長期間放置したままの状態では、火災保険への加入を断られる可能性があります。
保険会社は、火災リスクや損害発生の可能性が高い物件を敬遠する傾向にあり、管理が行き届いていない空き家は「高リスク物件」と判断されやすくなります。たとえば以下のような特徴が確認されると、保険審査においては不利になるでしょう。
- 屋根や外壁が著しく劣化している
- 草木が生い茂って敷地の出入りが困難
- 窓や扉が破損している
空き家を火災保険に適用させる場合には、定期的な点検・清掃や破損箇所の修繕など、最低限の管理が求められます。空き家であっても所有者としての責任を果たし、良好な状態を保つことで、火災保険加入はスムーズになります。
相続した空き家の火災保険加入に向けた対応

相続した空き家を火災保険に加入させる場合、以下の対応が必要です。
相続した空き家については、必要な手続きを早めに済ませることが重要です。それぞれの対応について解説していきます。
①保険契約者の名義変更が必要

相続した空き家に火災保険を適用するには、保険契約者の名義変更が必須です。元の所有者名義のままでは、補償の対象外となるケースがあるため、相続が発生した段階で速やかに手続きが必要となります。
名義変更の際には、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や相続関係を示す書類、登記簿謄本などが求められる場合があります。また、名義変更とあわせて保険の内容が現状に適しているかも確認し、必要に応じて補償内容の見直しを行うことも推奨されます。
空き家は管理状況や使用目的によってリスクが変わるため、名義変更と同時に保険会社へ現在の状況を伝え、最適な火災保険に加入するようにしましょう。
②用途が変わる場合は補償の見直しが必要

相続によって取得した空き家を活用する場合、用途が変わる際には火災保険の補償内容を見直すことが必要です。
例えば、これまで無人だった住宅を賃貸物件として貸し出す、あるいは事業用に転用するといったケースでは、保険の対象や補償範囲が適切でない可能性があります。
用途変更に伴い発生し得るリスクも変化するため、既存の契約内容では十分な補償を得られません。特に、第三者による損害や設備使用による火災リスクが増える場合には、それに対応した特約や補償の追加が必要です。
相続後に空き家の活用を考える際には、必ず保険会社に状況を伝え、用途に合った契約内容への見直しをおこなってください。
③無保険の場合は早めに新規契約を検討する

相続によって取得した空き家が無保険の状態である場合は、できるだけ早く火災保険の新規契約を検討しましょう。
相続直後は手続きや名義変更に追われがちですが、空き家は人の出入りが少ないために火災・放火などのリスクが高まりやすく、保険未加入のままでは損害を補填できません。特に古い家屋は老朽化が進んでおり、火災につながる要因が潜んでいる可能性もあるため、早期の保険手続きが必要です。
保険会社は相続後の状況に応じた補償プランを用意しているため、早めに相談することで適切な内容で契約できます。資産を守る観点から、無保険の空き家は放置せずに新規契約を結びましょう。
火災保険料を抑える方法

相続で取得した、もしくは既に所有している空き家を火災保険に適用させる場合、費用負担も大きくなるため、加入をためらう方もいるでしょう。以下の方法では、火災保険料を抑えることが可能です。
それぞれのポイントについて解説していきます。
建物への補償金額を引き下げる
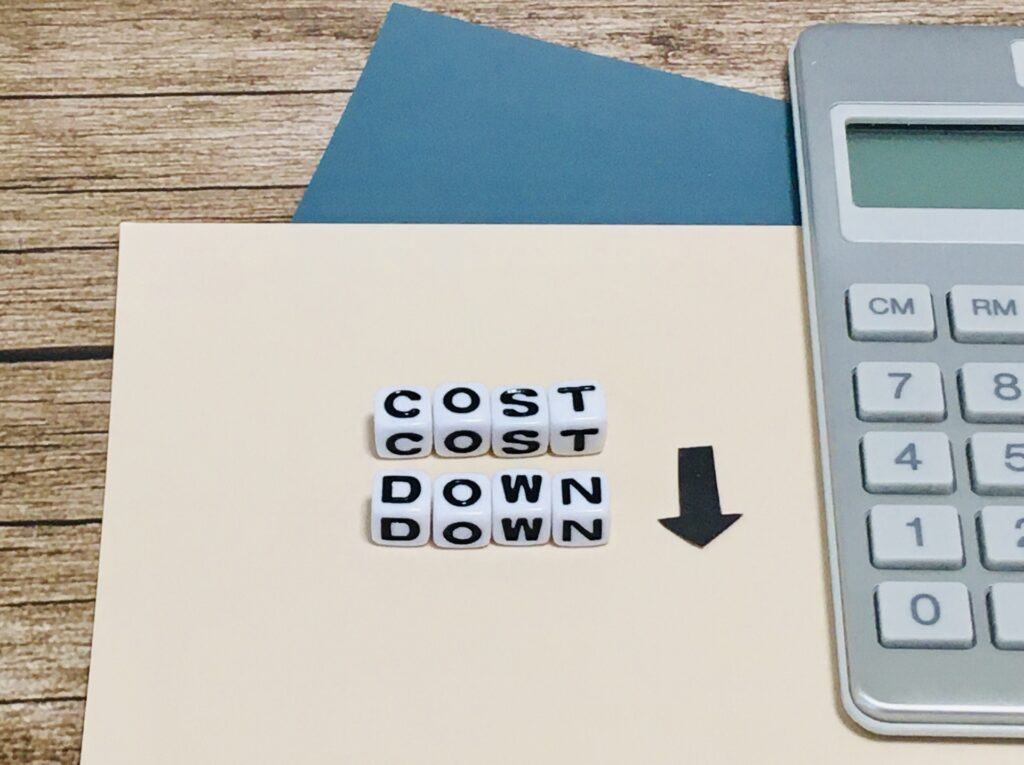
空き家の火災保険料を抑える方法の一つに、建物への補償金額を引き下げるという選択があります。
補償金額は建物の再建費用などに基づいて設定されますが、実際に住む予定がない場合や解体を検討しているケースでは、必ずしも高額な補償を必要としないこともあります。そのような場合には補償範囲を見直し、最低限の金額に設定することで、保険料を軽減することが可能です。
ただし、万が一の火災時には設定した補償額以上の保険金は支払われないため、建物の資産価値や用途を踏まえた上で保証金額を決定しましょう。保険会社との相談を通じて、コストと補償内容のバランスが最適なプランを選ぶことが求められます。
契約期間を長くして保険料を割り引く
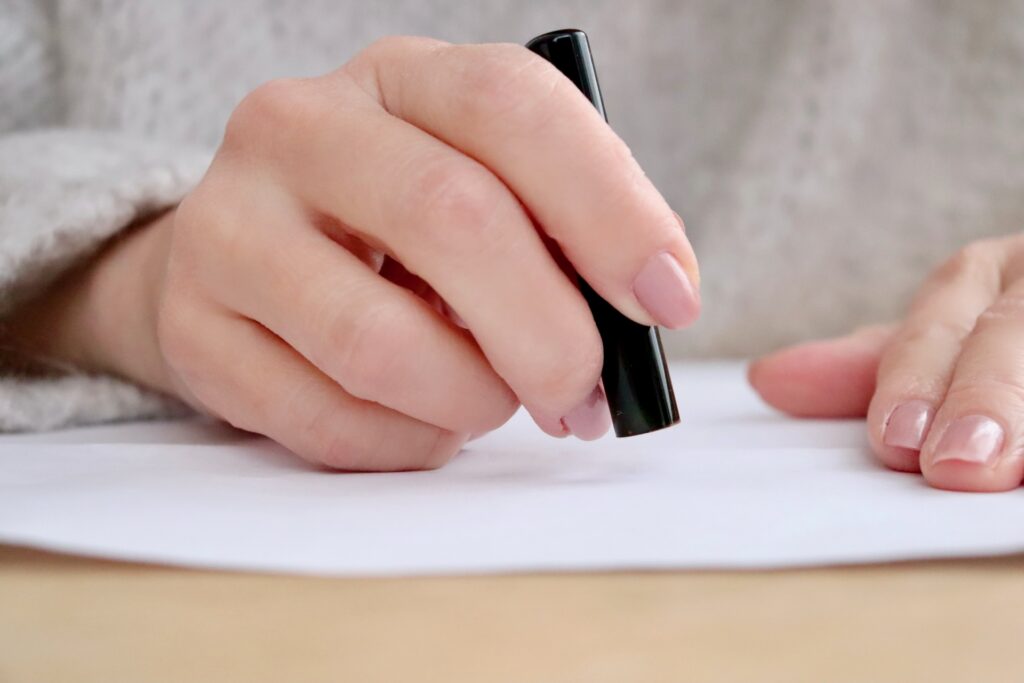
火災保険の契約期間を長く設定することで、割引を受けられるケースがあります。多くの保険会社では、1年契約よりも3年や5年といった長期契約を選ぶことで、総支払額が割安になるよう割引制度を設けています。
これは契約更新の手間を減らし、保険会社側の事務コストも軽減されるため、その分を保険料に還元するという仕組みです。空き家は短期間で使用予定がないことが多く、長期契約との相性が良い資産です。
また、長期契約中の保険料は途中で見直されにくく、保険料率の変動リスクが避けられる点もメリットと言えます。火災保険の見積もり時には、長期契約による割引の有無を確認し、費用負担を軽減する工夫を行うと効果的です。
家財補償を付けない内容で契約する

家財補償とは、建物内にある家具や電化製品などの動産を対象とした補償です。実際に居住していない空き家では、家財が存在しない、あるいは少ないケースが多く見られます。
そのため、建物の補償だけに絞った契約を選ぶことで、保険料の総額を削減することが可能です。また、保険の見直しや契約手続きも簡素化されるなど、シンプルな契約によってメリットを受けやすくなります。
ただし、管理目的で設置した最低限の設備がある場合は、それらの補償の必要性についても検討が必要です。実態に即した内容で契約することで、費用を抑えつつ最適な保険を選択できます。
西湘エリアの空き家相談ならハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめ

西湘エリアで空き家の相談先をお探しの方には、ハウスドゥ 小田原市役所前がおすすめです。同店は小田原市荻窪に位置し、地域密着型の不動産サービスを提供しています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 屋号 | ハウスドゥ 小田原市役所前 |
| 会社名 | 株式会社Forest field |
| 所在地 | 〒250-0042神奈川県小田原市荻窪531-6 |
| 電話番号 | 0465-34-2555 |
| 公式HP | https://odawarashiyakusyomae-housedo.com/satei/ |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第31148号 |